4月の資産状況とトレード成績。
前半は安全情報確保支援士の勉強、後半はスレイザスパイアをやってた月だった。
貸借対照表

4月の貸借対照表はこんなかんじ。
先月比で大体10万のマイナス。
4月の初めにロングしたオプションが20万近いマイナス出てる。
あとは仮想通貨のマイナス分か。
先月初の資産1300万超えを果たしたところだったが、1か月で陥落してしまった。
損益計算書

収支はこんなかんじ。
手帳は四月始まりを使う主義なので、それが日用品?として計上。
とはいえ在宅になってからあまり使わなくなったが。。。
ただ過去を振り返ってもしっかり手帳でスケジュール管理できてると公私ともに充実してるし、しっかり管理していこう。
トレード結果
冒頭に書いた通り久々に新規ポジションをとったが損切りができずに大きな損失となってしまった。
本来は来月に書くべきだが、証券会社のシステムからデータが消えちゃうから今書く。
合計損益
ポジションは2022/05限23000Pのロング。
1枚59円で3枚ロングしたため、最大損失は約18万円。
4円で損切りしたので、16万5千円のマイナス。
トレード反省
チャート確認
まずはオプションの価格チャート。
十字線でクロスしているところが仕掛けポイント。
オプションは時間で価値が減衰していくため右肩下がりのチャートとなっている。
このため逆に売り方であれば16万円の利益を出せたわけだが、プット裸売りはやらない主義なので考察はしない。
仕掛け後の最高値は4/7の72円。
仕掛け値59円を超えた日は5日あった。
このため利確できるタイミング自体はまぁまぁあり、今回の損切りはしっかり利確ラインを決めれていなかったことが原因といえる。

次に原資産である日経225先物のチャート。

プットロングのため目線は下。
チャートを見てわかるように目線は悪くなく、最初の数日は27600よりも上に行ったが、その後は下げて26200近辺をつけた。
もし先物ショートをしていれば1500円近く取れていた目線とタイミングだった。
以上から(結果論なのだが)問題だったのは以下3点と推察。
・先物ではなくオプションを選んだことが問題
・オプションの売買タイミングが問題
・オプションの限月、ストライクの選定が問題
先物ではなくオプションを選んだことが問題
そもそもオプションを選んだ理由は、損失額限定と利益時の爆発力を期待したため。
先物で考えて損切りライン自体は仕掛け前に決めていて、直近高値の28,415円。
仕掛け値の段階から考えると損切り額が大きくなるためオプションを選んだ背景もある。
仮に先物だった場合、ロスカットまで800円程度の幅となり、オプションと同じ最大損失で2枚は仕掛けられたかなという感じ。
結局オプションでも引っ張てしまったことを考えると先物ミニ2枚が正解だったわけだが。
ただ全面的にオプションを選んだことが間違いかと言われると、肯定はできない。
ボラティリティが爆発すれば先物以上の利益になるのは理論的にも経験的にも明らか。
今回はそこまでの変動にならなかったというだけとも言える。
では何が問題か。
そもそも今回の買いはFOTMなので原資産の値動きによる利益は大したことはない(はず)。
となるとボラティリティを期待したロングなわけで、そこに注目できていたかと言われるとできていなかった。
この意識の欠如が問題かなぁ。
結果として次のオプション売買タイミングの問題につながるわけだし。
ただただ安易に先物の代替としてオプションを選んでしまい、何をロングしているのか、逆に何をショートしていたのか認識不足だった。
今回でいうならベガロング、シータショート?だった。
この意識を忘れないように次のトレードに活かす。
オプションの売買タイミングが問題
これは大いに問題がある。
仕掛けた当日は日経が大きく下げた日であり、仕掛け数時間で十数%の含み益が出ていた。
時間効率で考えればかなり良いタイミングで、そこで利確できてもおかしくなかった。
そのあとも数日利益が出せるタイミングがあったが利確できなかった。
というのも原資産の先物が仕掛け当時よりも下げていたため、先物を売っていた場合の利益と比較して見劣りしており、もっと行けると考えてしまったことが要因。
これもベガをロングしていることの理解が不足していたことに起因する。
またシータの価値減少を甘く見くびっていた。
ロングの場合、待てば待つだけ不利になるということを理解しながらも自分の建値を意識してしまった。
どちらも意識の欠如と建値に対する執着が根底にある。
また損切りラインを決めていなかったことも問題。
先物換算で損切りラインは決めていたが、オプションでの損切りラインは決めれていなかった。
ボラティリティが爆発した際は利確基準が難しいから損切りラインも一緒くたにして見ないようにしてしまった。
次からは建値に対しての執着をなくす(減らす)ことと、たとえ難しくてもしっかり利確/損切りラインを定めてから仕掛けるようにする。
オプションの限月、ストライクの選定が問題
これは上2つに比べたらあまり大きな問題ではないと思う。
というのもしっかり損切り/利確できていれば、限月やストライク選択の影響は少ないはずのため。
確かに1つ限月が先の同値ストライクのプットを見ると、同じ期間でも値下げ率はやはり違う。
ただし、これは限月が近いほうがシータの減少率が大きいから。
この影響が大きく出るような場合はロットが大きいか、保有期間が長いかくらいなので、短期の小ロットの売買では大きな影響にはなりえないと考える。
三日後期限とかでない限りは1か月先のもので基本は大丈夫なはず。
ここに注力して改善するよりは前述の二つの課題を改善する。
まとめ
久々に新ポジションをとった月だった。
結果失敗に終わったが、これを糧に次に活かそう。
とはいえ塩漬け銘柄もまだ健在で、プラスになるビジョンが見えない。
やはり短期でトレードを繰り返して、損切りできないマインドを打破することが重要かもしれない。



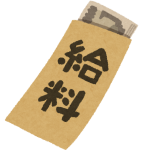
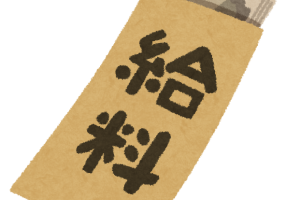
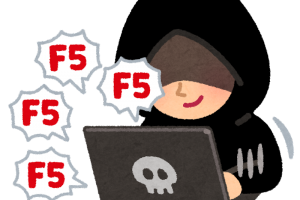



コメントを残す